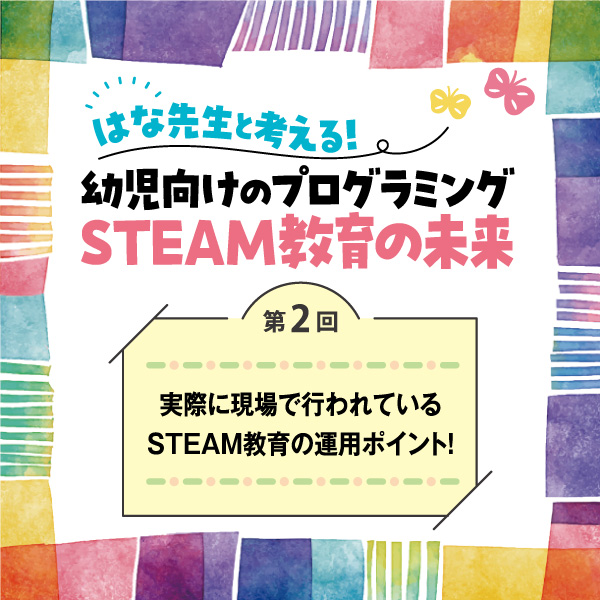第1回 幼児向けプログラミングやSTEAM教育の目的は?──はな先生と考える! 幼児向けのプログラミングSTEAM教育の未来
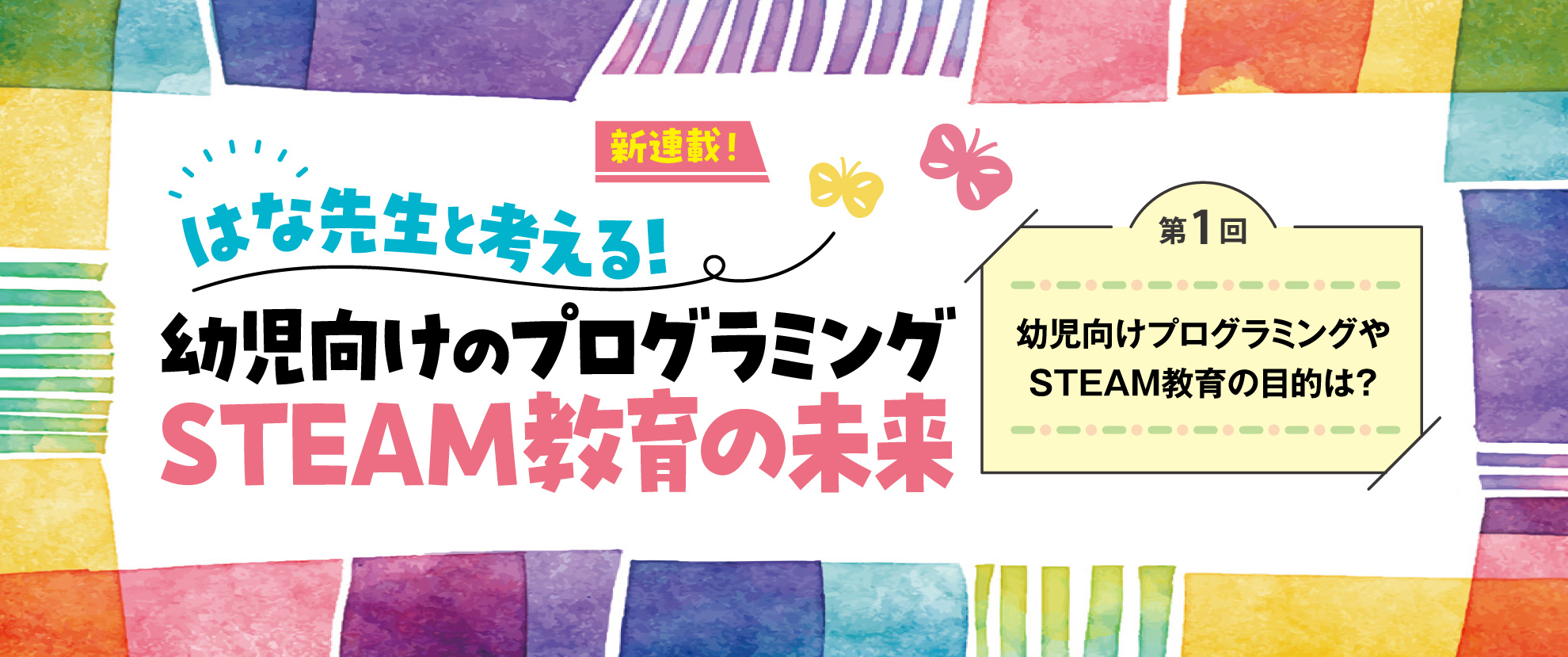
はじめまして。幼児向けSTEAM教育の専門家“はな先生”です!
近年、子ども向けのプログラミングやSTEAM教育が注目され、保護者の方からも「うちの子にもやらせたい!」という声が増えています。幼稚園や保育園でも、最先端の教育を取り入れる動きが広がり、当社にも多くの問い合わせが寄せられています。
そこで、4回にわたり幼児向けのプログラミングやSTEAM教育について一緒に考えていきましょう!
幼児向けプログラミング教育の目的
幼児向けプログラミングでは、文字や数字が読めなくても使える「ビジュアルプログラミングツール」を活用します。子ども達は直感的に絵を動かしたり、簡単なゲームを作ったりしながら、遊び感覚でプログラミングを学びます。
では、その目的は何でしょう?「スキルを身につけるため」? 「小学校の授業についていくため」?
実はどちらも違います。
本当の目的は、論理的思考力や問題解決力、粘り強さといった非認知能力を育てることです。
「どうやったら思い通りに動くかな?」と試行錯誤することで論理的思考力が身につき、「うまくいかないプログラムをどう直せばいい?」と考えることで問題解決力が養われます。
また、失敗しても挑戦し続ける経験が、粘りさや創造力を育みます。

STEAM教育との繋がり
STEAM教育は、科学・技術・工学・アート・数学を組み合わせた学びで、知的好奇心や創造力を育むことを目的としています。
特に幼児期は「なんで?」「どうして?」と疑問を持ちやすい時期。この時期にSTEAMの考え方を取り入れることで、より深い探究心を育むことができます。
また、幼児期(特に5歳まで)は非認知能力が最も伸びる時期とされています。子ども達は遊びを通じて学びながら、「知ることの楽しさ」を体験し、主体的に考える力を身につけていきます。この時期にSTEAM教育を取り入れることは、将来の学びの土台を築く上で非常に重要です。
これからの時代に求められる力
AIやロボット技術の進化により、未来がどうなるか予測が難しい時代になっています。その中で子ども達に求められるのは、「決められたことをこなす力」ではなく、「自分で考え、創造し、問題を解決する力」です。
幼児教育においても、従来の学びを大切にしながら、時代に合った「+α」の学びを取り入れることが重要になっています。世界ではすでにプログラミングやSTEAM教育が幼児期から導入されていますが、日本ではまだ普及が進んでいません。今後、より多くの園でこうした教育が取り入れられること期待しています!
次回は、実際に現場で行われている幼児向けプログラミングやSTEAM教育についてご紹介します。お楽しみに!
(MiRAKUU vol.50掲載)
-

- 株式会社MIRIDE代表取締役
新卒入社したITベンチャー企業でいくつもの新規事業を成功に導き、取締役を歴任。
この経験より幼少期の非認知能力の重要性を実感し、未来の子ども達のために起業、当社設立。