第11回 病気や障がいを防ぐにはどうしたらいいの?(前編)
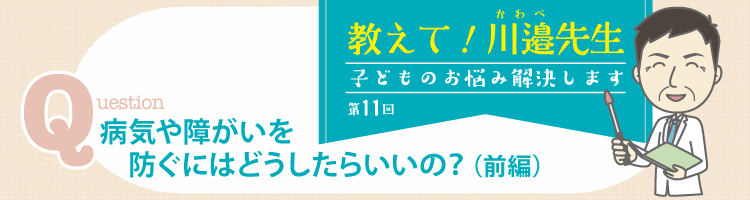
病気や障がいを防ぐには、自立がポイントとなります。
永久歯は大きくなってから乳歯の後に生えてくると思われていますが、実はもとになる歯の種(歯胚)は母胎にいる時に既に作られています。受胎から生後1か月で永久歯のほとんどが母体内でできているのです。また、ほとんどの機能の方向性が、出来上がっています。学校で同じように勉強を教えてもらっても、人によってできる・できないがあります。このできる・できないというのは、実際には受胎から生後1か月でほとんどの機能の方向性が、出来上がっています。
その後の成長も、親が育てると社会性が身に着きにくく、自立も遅いです。社会が育てれば、この問題は最小限で済むのです。教育の最初を、できれば生後2か月~6か月に始められれば、今言われている日本の問題はほとんど防げるでしょう。
子どもの自立は、親の自立でもあります。多くの親達は10歳になっても子どもを抱いています。そのようにされている子ども達の未来の問題は、予防できるはずがありません。
通常の日本人の感覚では、障がいがあれば、かわいそうな子どもとして、何もさせずに全部周りがしてしまいます。しかし1歳を過ぎると、自分でやらなかった子どもは、本当に障がいがあろうがなかろうができなくなってしまうのです。親の言う通りにしないと叱られるが、自分が泣けば親が全部やってくれるというパターンを学習するからです。
子どもの成長で、必要な親の方向性は、自立と社会性です。発達とは、教育そのものなのです。成長に合わせてできることを増やす。昨日の自分よりも今日の自分が成長することが親子の成長です。子どもだけ良くなるということはないのです。
未来歯科で最初に説明するのは、子どもに対しての教育ではありません。子どもの成長と、発達を応援し、親も元気にできることを増やし、子どもと競争してもらうことを約束してもらいます。ほとんどの親が、嚥下機能も、姿勢も、態度も問題があることが多く、その検査も同時に行います。原因が親だとわかると、一緒に成長してくれることになるので、そこからの子どもの成長は全く違うのです。
子ども達は親から自立すると、一気に呼吸と嚥下の成長を始めます。そうなると、親は、頑張ってよかったと、呼吸と嚥下は教育だと理解します。しかし、健康を大きく害しているにも関わらず、理解ができず協力しない親もいます。
親の笑顔と協力がある子ども達は、自分ができるようになってくると未来歯科に来ることを喜びます。しかし、楽しく笑顔でいてくれない親の子どもは、家でのトレーニングも全くしないし、未来歯科へも嫌々来ます。結果は一目瞭然です。できたことを喜び、できないことは何度もトライする、その時に親の協力が必要なのです。
子どもの未来をあきらめないこと。そして教育は、できないことを理解し、決して叱らない、怒らない、できたら褒めて、できなかったらもう一度トライさせる。目的を持たせて、子ども達の未来を一緒に語るのが、親です。叱るには、アイデンティティで応援するように叱りましょう。「あなたはできる子だから、頑張って」「あなたは格好いいんだから、かっこよくね」など、必ず最後は応援するようにして落とさないこと。そうすると、子どもの成長を楽しむ親になります。
生後3か月までは、動物脳の発達が見られるため、抱かなければ赤ちゃんはシナプスを急速に作りだします。その後、そのシナプスは徐々に減り、新しいシナプスができ始めます。
生後8か月がピークです。生後3か月までは体をしっかり動かすようにさせます。すると、できることが増えます。生後6か月になると捕食の動作から始まり、手で掴んで食べるという動作ができるようになり、離乳食が取れるようになってきます。抱かない、触る、声をかける、口を大きく開かせる。反射を使って体をよく動かすのが基本です。生後8か月くらいになると、目からの情報が強かったのが耳もしっかりと聞こえるようになり、五感が整い始めます。
このシナプスは、動物としての機能を作り上げるために、必要なだけ、動かしただけ成長します。3歳になっても歩けない子どもが増えているのは、このトライすべき時期に親が抱いてしまい運動機能の発達を妨げてしまったからです。このような子ども達は、成長、発達が遅れるというよりも、1歳までにできることを、たくさんにしてあげていないから、できないのです。この時期には、親は見守り、できることを楽しむ、危険な場合にだけ抱くという習慣を作ることです。赤ちゃんの教育は、子どもの教育ではなく、親の教育が問題なのです。よく5歳くらいになると「言うことを聞かない」と親が嘆くのですが、この問題は自立させてあげたかどうかが大きく関係しているのです。
また、生後3か月から8か月くらいまでは、どんな言語も覚えられる、目からの情報を取り込む能力があり、8か月から1歳くらいまでは、最も脳が発達するので、立ち上がることに何千回とチャレンジして、体を作り上げます。多くの人を見て視野を広げ、真似をすることで、社会性ができあがります。早期に多くの人の口元の動きと体の動きを見せることで、3歳で3か国語の言語発達を促すことができるのです。人見知りを作り上げると成長が数年は遅れます。多くの人に早期から会い、その時間を多くすることで、子どもはとても伸びます。生後3か月までの成長を止めないことが大切です。
(MiRAKUU vol.26掲載)
お問い合わせボタンからお気軽にご質問ください。
ご質問は、誌上・web上で公開されることがあります。また、必ずしも質問が取り上げられるとは限りません。ご了承ください。
-

- 新橋 未来歯科 院長
姿勢咬合セミナー主幹(27年以上続く姿勢と噛み合わせの歯科医師向けのセミナー)
Ken'sホワイトニングセミナー主幹1984年静岡県菊川市にかわべ歯科を開業。2011年新橋に未来歯科開業。
従来の疾患中心型治療ではなく、「細菌単位でのお口の中のリスクを知り、その結果に基づき改善していく」「食事内容の分析・アドバイス」「姿勢指導や、呼吸などのアドバイスによる体質改善」「患者様の未来の目標設定」をコンセプトにした「予防」診療を行う。
歯科医・歯科衛生士向けの各種セミナー、DMMでのオンラインサロン等も精力的に行なっている。
ホームページ:https://miraishika.com/
未来歯科アカデミー:https://miraishika.com/academy/
未来歯科アカデミーでは実際に未来歯科に来ていただくほか、リアルタイムでの質問も受けています。




