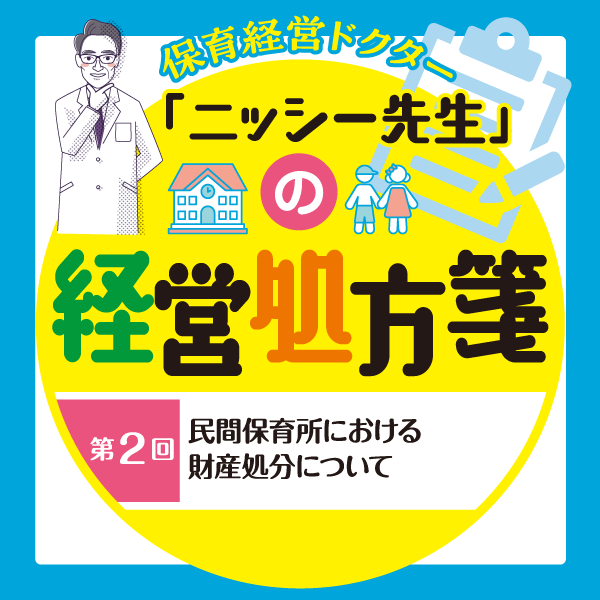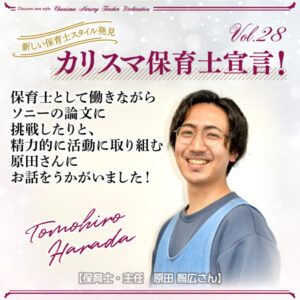第1回 私立保育所に対する委託費の弾力運用について──保育経営ドクター「ニッシー先生」の経営処方箋
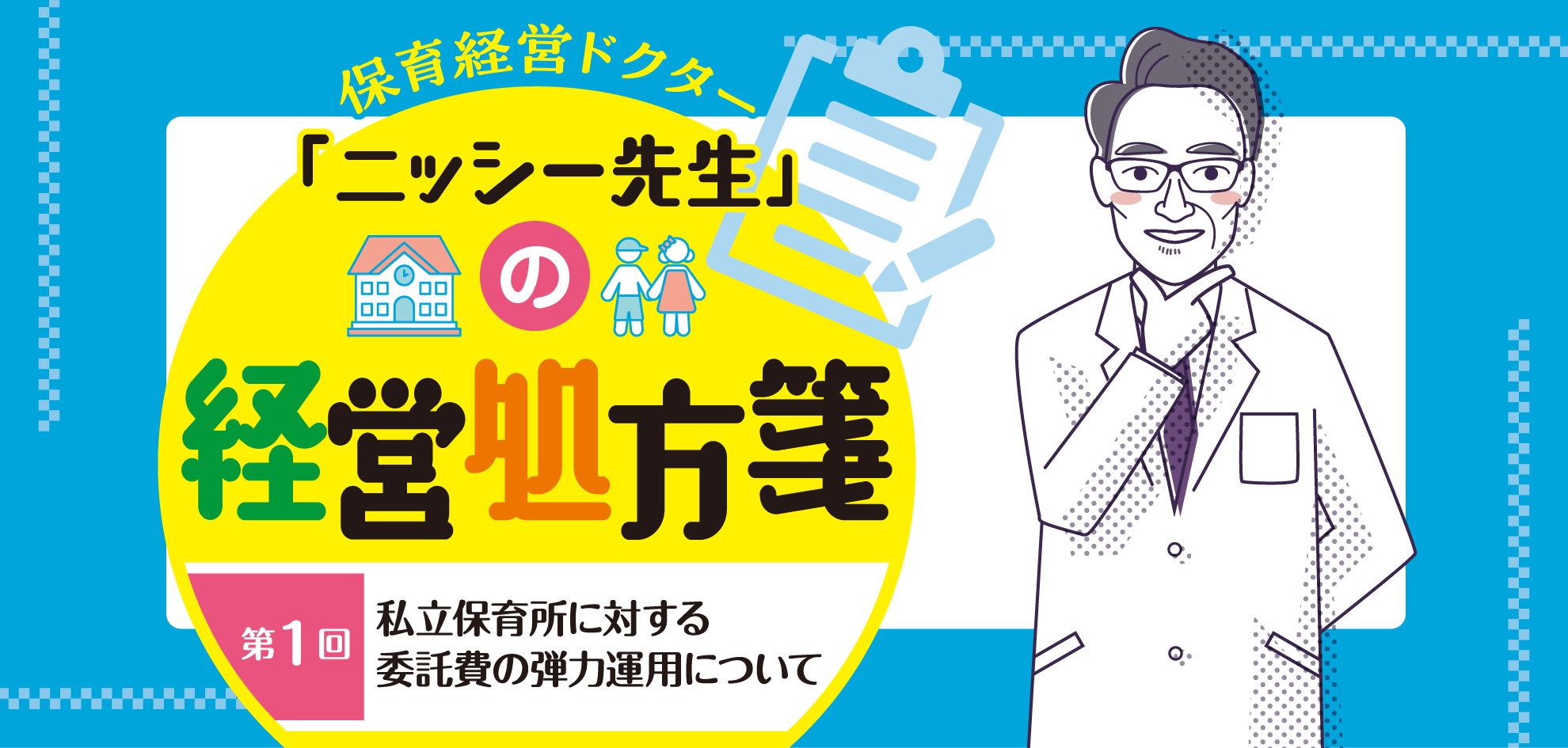
こんにちは。保育経営ドクター「ニッシー先生」です。
本連載では、保育施設の経営者の皆様が「現場ではなかなか聞けないけど実は気になっている」経営実務のポイントを、なるべくわかりやすく、そして実践的にお伝えしていきたいと思います。
私立保育所に対する委託費の弾力運用について
さて、記念すべき第1回のテーマは「私立保育所に対する委託費の弾力運用」について。
これは、実際に私のもとにも多くの園長先生から寄せられるご相談の1つです。
「行政認可保育所に対して給付されている委託費を弾力的に活用したいが、その取り扱いについてどう進めていいか分からない」
──まさに現場のリアルな声ですね。
この「委託費の弾力運用」とは、簡単にいえば、本来の使途以外にも一定の条件を満たせば柔軟に運用できるという制度です。とはいえ、その根拠や制限、運用の具体例が複雑で、どこまでOKなのかが曖昧になりがち。現場で戸惑うのも無理はありません。
実際には、この制度のベースは「子ども・子育て支援法」などで定められていますが、重要なのは【その解釈と運用方法】です。これらは国の通知や自治体の判断によって変わることもあるため、個別のケースに応じて丁寧に対応していく必要があります。
例えばこんなケースがあります。
例① 整備積立資産を例別拠点で活用したい
保育園の整備目的で積み立てた資産を、他の拠点で使いたい場合、「同一設置者の運営する社会福祉施設等」に必要な①建物・設備の整備や修繕、土地取得、②賃借料、③それらにかかる借入金の返済・積立、④租税公課に充当することが可能です。
ただし、使用には「処遇改善等加算基礎分の範囲内」という上限がありますので、無制眼ではありません。
例② ー前期末支払資金残高の取り崩し
こちらも多く寄せられるケースです。運営に必要な資金が足りないタイミングで、前期の余剰金を活用したいという相談です。
この場合も条件を満たせば活用可能で、使途としては①法人本部の運営費、②同一設置者による第一種・第二種福祉事業の運営や施設整備、③公共事業への支出が認められています。
重要なのは、「当該施設の運営に支障がないこと」を前提にすること。そして、役員報酬に充てたい場合は、事前に勤務実態に応じた役員報酬規程の整備が必要になります。
委託費の弾力運用は、きちんとした知識をもって対応すれば、法人経営の自由度を高める非常に有効な手段です。ですが、ルールを誤解していたり、口頭での相談だけで済ませてしまったりすると、後から行政に指摘されるリスクも。
だからこそ私は、「まずは管轄行政に具体的に相談すること」「記録を残すこと」をおすすめしています。
今回の内容が、経営者の皆さまのヒントや安心材料になれば幸いです。
次回も有益な情報をお届けいたしますのでお楽しみに!
(MiRAKUU vol.51掲載)
-
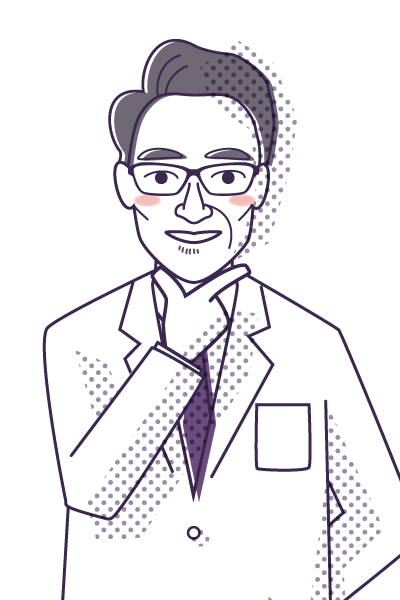
- 保育経営ドクター
複数の事業会社の経営に携わった後、経営コンサル会社で30社以上の再建に成功。その実績を活かし、現在は保育業界に特化した経営支援を行う。
「現場に寄り添う経営パートナー」として、多くの園長・施設長から信頼を集めている。