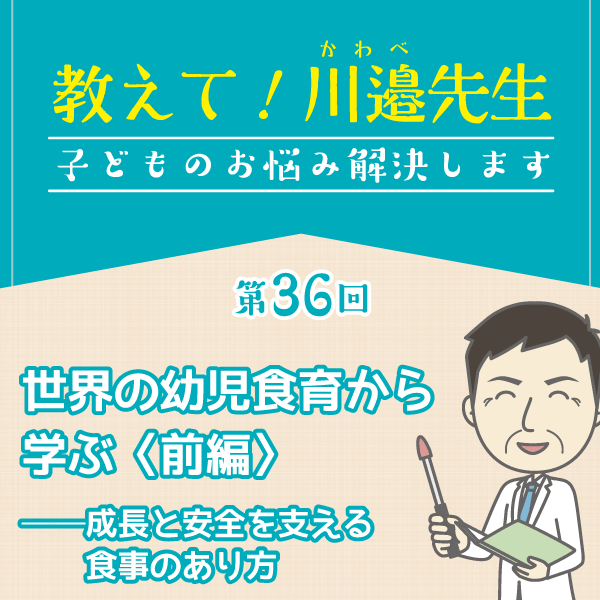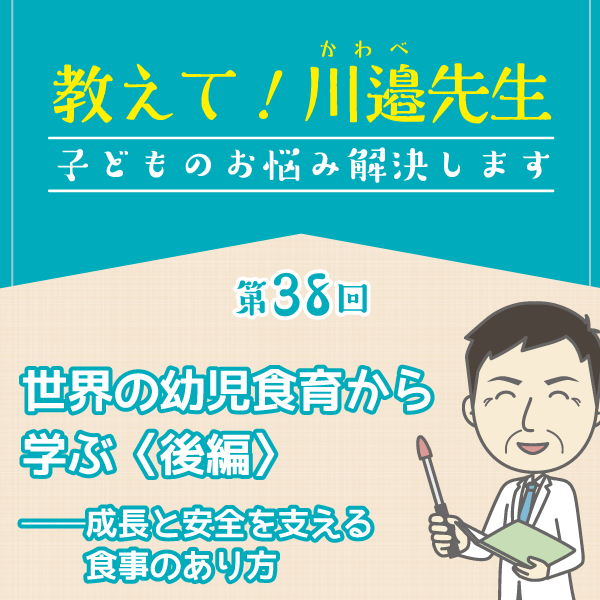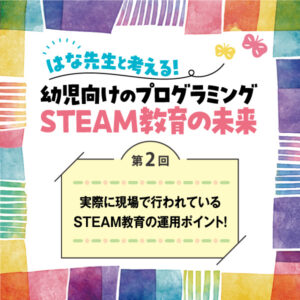第37回 世界の幼児食育から学ぶ〈中編〉──成長と安全を支える食事のあり方──
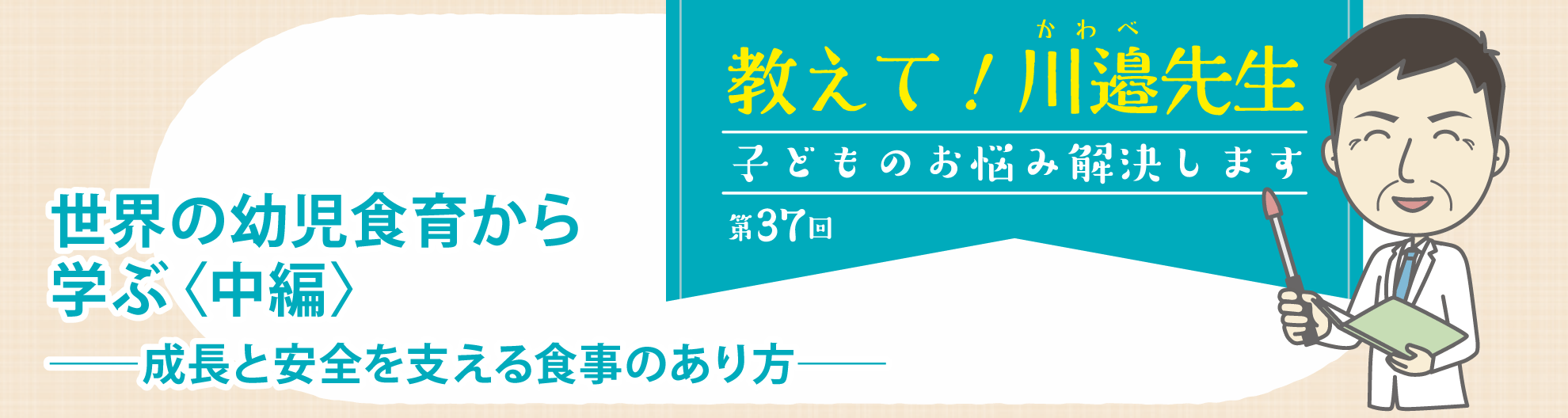
前回に引き続き、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、アメリカなど世界各国の幼児食育の特徴と工夫を紹介し、特に日本の幼児食における窒息リスクへの対応と各国の食事形態の違いに焦点を当てて考察します。
デンマーク・ドイツの幼児食育──子どもの主体性を尊重するアプローチ
3-1 デンマークの食育──子どもの意思を尊重する4つのステップ
デンマークの食育は、子どもの意思を尊重し、強制せずに食への興味を育むことを重視しています。
- 世間のダイエット風潮から子どもを守る
- 体型や見た目について不安にさせる話をしない
- 性格をほめ、食べ物の善し悪しを親が判断しない
- 食事を「健康のため」と強調せず、楽しさを重視する
- 身体のシグナルに耳を傾ける
- 細かい食事ルールは体が欲するシグナルを聞き逃す恐れがある
- 必要以上に食べさせない、過度に制限しない
- お腹の満足感を意識させる練習をする
- 野菜との関わり方
- 野菜とのふれあい、においをかいだり触れる機会を作る
- 無理やり食べさせない
- 大人が美味しく食べている姿を見せる
- スイーツの力を借りる
- お菓子の禁止は、逆に魅力を高めてしまう
- 週に数回、スイーツの時間を設ける
- 甘いものへの不健全な執着を取り除く
デンマークの幼稚園では、「幼児に親のペースで力ずくで食べさせるのではなく、お子さんのペースで食事をすることが重要」と考えられています。日本のように食材を細かく刻んで提供するのではなく、子ども自身が食べやすい大きさに調整できるよう援助します。
3-2 ドイツの幼児食育──共同体験と自立の重視
ドイツの幼稚園(キンダーガーテン)での食事には以下のような特徴があります。
- コミュニティとしての食事体験
- 弁当持参ではなく、皆で同じ食事を共有
- 大人も子どもと同じ食事を取り、会話を楽しむ
- 食を通じた社会性の発達を重視
- 自立心を育む環境づくり
- 3歳からローテーションでテーブルセッティングや後片付けを担当
- 3歳以上は自分で食事を取り分け、小さな子どもはバディ制度でサポート
- 年齢に応じた責任と役割を持たせる
- 健康的な食習慣の育成
- デザートは果物が基本、甘いものは限定的
- おやつには生野菜スティック(きゅうり、人参、パプリカなど)
- シュガーフリーポリシーを採用する園が増加
ドイツの幼児食では、日本のように窒息リスクを避けるために食材を細かく刻むよりも、適切な大きさの食材を提供し、じっくり噛んで食べる習慣を育むことを重視しています。例えば、生野菜スティックは日本では窒息リスクが高いと考えられがちですが、ドイツでは日常的におやつとして提供され、子ども達は早い段階から安全な食べ方を学びます。
北アメリカの幼児食育──科学的根拠に基づく安全対策
4-1 アメリカにおける窒息予防ガイドライン
アメリカでは、疾病管理予防センター(CDC)や米国小児科学会(AAP)が、科学的根拠に基づいた窒息予防ガイドラインを提供しています。
- 年齢に応じた窒息リスク食品のリスト
- ナッツ類、グミキャンディ、ポップコーン、ホットドッグなどの具体的な危険食品リスト
- 4歳未満の子どもには丸くて固い食品を与えないよう推奨
- 食品の調理・提供方法
- 生野菜は小さく切る(1/2インチ=約1.3cn以下)
- ブドウは縦半分または4等分に切る
- ピーナッツバターは厚塗りではなく薄く塗る
- 食事環境と監視
- 食事中は座って食べる(寝転がった状態、歩き回る、走るなどしない)
- 車や乳母車の中での飲食を避ける
- 食事中は常に大人が見守る
アメリカのガイドラインは「禁止」よりも「適切な提供方法」に重点を置いている点が特徴的です。例えば、ブドウや小さなトマトは禁止するのではなく、「4等分に切る」という具体的な調理法を提案しています。
4-2 アメリカの多面的な食育アプローチ
アメリカの保育施設では、窒息予防だけでなく、総合的な食育アプローチが実践されています。
- 多面的な介入プログラム
- 「Color Me Healthy」や「Eat Well, Play Hard」などの介入プログラム
- 野菜や果物の摂取量増加に効果を示す科学的根拠
- 園芸活動を取り入れた食育の実践
- 教師のモデリングと環境づくり
- 教師が同じ食事を取り、積極的に食べる姿を見せる
- 落ち着いた食事環境の提供
- 肯定的な声かけと強化
- 実践的な食の体験
- 調理体験や食材に触れる機会
- 食材の色、形、香りなどを五感で体験するアクティビティ
- 食を通じた科学的思考の発達促進
アメリカの食育では、単に窒息リスクを避けるだけでなく、子ども達が食材に興味を持ち、積極的に新しい食べ物に挑戦する姿勢を育むことを重視しています。
(MiRAKUU vol.52掲載)
お問い合わせボタンからお気軽にご質問ください。
ご質問は、誌上・web上で公開されることがあります。また、必ずしも質問が取り上げられるとは限りません。ご了承ください。
-

- 新橋 未来歯科 院長
姿勢咬合セミナー主幹(27年以上続く姿勢と噛み合わせの歯科医師向けのセミナー)
Ken'sホワイトニングセミナー主幹1984年静岡県菊川市にかわべ歯科を開業。2011年新橋に未来歯科開業。
従来の疾患中心型治療ではなく、「細菌単位でのお口の中のリスクを知り、その結果に基づき改善していく」「食事内容の分析・アドバイス」「姿勢指導や、呼吸などのアドバイスによる体質改善」「患者様の未来の目標設定」をコンセプトにした「予防」診療を行う。
歯科医・歯科衛生士向けの各種セミナー、DMMでのオンラインサロン等も精力的に行なっている。
『かわべ式 子育てスイッチ ~生まれた瞬間からグングン発達する88の秘訣』(エッセンシャル出版社)好評発売中。
ホームページ:https://miraishika.com/
未来歯科アカデミー:https://miraishika.com/academy/
未来歯科アカデミーでは実際に未来歯科に来ていただくほか、リアルタイムでの質問も受けています。