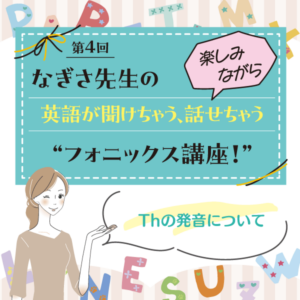絵本の頭の先から足の先まで全部届けたい──聞かせ屋。けいたろうさん

絵本との出会いは短大で
編集長:けいたろうさんは子ども向けに絵本の読み聞かせをされていますが、他にもされているのですか?
けいたろう:そうですね。保育園・幼稚園、イベント等での読み聞かせのほかに、保育園・幼稚園の先生向けの研修会や、図書館などで行なっている絵本読み聞かせのボランティアさん向けの講習会、保育専門学校のゲスト講師などをしています。
編集長:きっかけは何だったのですか? 小さい頃から絵本が好きだったと
か。
けいたろう:いやいや、全然そんなことはなくて(笑)。僕は宝仙学園短期大学で保育を学んでいたのですが、授業で毎回絵本を読んでくれる先生がいて、それをクラスメイトが毎回楽しみにしていたんですね。それを見て、大人でも絵本って面白いのではないかなと思ったのが始まりです。
編集長:絵本との出会いは大人になってからだったんですね。意外です。
けいたろう:そうなんです。両親はたくさん遊んでくれたし、関わりは密にしていましたが、絵本はあまり読んでもらっていないんです。ですから、懐かしいというより、初めて見る絵本が面白いという感じでしたね。

編集長:いつ頃からこのお仕事をしようと思ったのですか?
けいたろう:路上で読み聞かせを始めたのは2006年の10月、卒業まであと半年という時期です。就職活動で公立保育園一本に絞ったのですが、落ちてしまって。それで、読み聞かせの活動をしながら公立の保育士を目指そうと思ったんです。もちろんこれだけでは仕事にならなかったので、初めの2年間は非常勤で保育士をしていました。この時期、読み聞かせは週末が中心でしたね。
編集長:短大で絵本の面白さに出会って、卒業してそのままこのお仕事をされたと。
けいたろう:はい。小さい頃は歌手とか芸能人になりたかったんです。人前で何かしたり、目立ったりするのが好きだったんですね。ちやほやされるのが好きだったんじゃないですかね(笑)。そういう部分は繋がっているかもしれませんね。
自分が感じるままに読み聞かせを
編集長:絵本を読み聞かせする上で大切にしていることは何でしょうか?
けいたろう:自分ではなく、絵本が立つようにと思っています。また、一つひとつが大事に見えるように、たとえばできるだけ手が絵を邪魔しないようにだとか、絵本がしっかり綺麗に見えるように持ったりとか、そういう部分にも気を付けていますね。表紙のすぐにしていて、絵本の頭の先から足の先まで全部届けたいというのが僕のスタイルです。
編集長:読み聞かせ方として、感情を込めた方が良いという意見と淡々と読んだ方が良いという意見がありますが、どうお考えですか?
けいたろう:声色や抑揚をつけるかどうかというのは色いろ言われる話ではありますが、あまり囚われなくてもいいかなと僕は思っています。
「聞かせ屋。」というからには、すごく抑揚もつけて芝居がかって、という印象を受けている方もいらっしゃるんですが、僕は絵本の絵を見てほしいと思うし、演出過多になってしまうと絵本が大事に伝わらないのではないかなと思うので、意外と演出はしないんです。
あまりに芝居がかってしまうと、絵本よりも自分の方が立ってしまうんですね。最初の頃は、僕も声色をつけて読み聞かせをしていたし、登場人物それぞれの声色の練習もしていました。ところがある時、鬼の絵本を読んだ時に、「お前の目玉をな~~」と芝居がかって読んでいたら、子ども達がみんな僕の方を見ていたんです。その時に、ちょっと違うなと思ったんですね。それから、絵本に目を向けてもらうにはどう読めばいいかと考えながらやるようになり、読めば読むほどシンプルになっていったんです。
とはいえ、声色がまったく変わらないなんてことありませんよね。読んでいる自分もその絵本を楽しんでいるし、その物語を感じて考えているわけで、当然ゾウの声と小さな女の子の声は違ってくるでしょう。自分が感じるままに声色が変わるというのが自然なのではないかなと思っています。
自分が好きな絵本、楽しいと思える絵本を
編集長:自然と読む形が良いということですね。たくさんの絵本がありますが、おすすめの絵本や、選び方のアドバイスをお願いします。
けいたろう:音楽や映画にも好みがありますよね。それと一緒で、自分が読みたい、子ども達に紹介したいと思う絵本を見つけると良いと思います。そうすると偏ってしまうという話を聞きますが、保育園も幼稚園もチームプレイなので、僕はこの絵本が好きだからこれを読む、あの先生は昔ながらの名作を大事にしているからそれを読むという風に、うまくバランスを取れるのではないかと思います。気持ちは声を通して伝わります。むしろ、自分が好きな話じゃないと伝わらないんですよ。苦手な所を無理してやっても、子どもにはバレますからね(笑)。まず、その絵本を楽しんで読むこと。好きな絵本を読むこと。そして、自分が楽しめる絵本を読むこと。そういう絵本選びをしてほしいなと思います。
絵本は絵と文で成り立っています。絵を見て楽しんでもらうのも、物語自体を楽しんでもらうのもどちらも大事ですけれども、絵本の場合はバランスがとても大事だと思うんです。絵と文が助け合っている、補い合っている。そういう、絵と文のバランスの良い絵本というのは、本当に絵本らしいし、絵本で出ている意味があるなと思いますね。
編集長:最近は、子ども向けでも泣いちゃうようなこわ~い本がありますね。

けいたろう:そうですね。トラウマになるような怖い話を選ぶ必要はないと思いますが、楽しい、嬉しい、悲しいなど色いろなことを感じるのは無駄ではないと思います。お父さんお母さん、先生、友達など、一緒に聞いて共感してくれたりフォローしてくれたりする人が周りにいるうちに、怖いという経験をしてもいいのではないでしょうか。
編集長:今後はどのように活動していきたいと思っていますか?
けいたろう:今がベストだと思っているんですよ。というのは、本来絵本は手元で楽しむものだと思っていて、そう考えると、絵本の読み聞かせというのは少人数の方が良いと思う。絵本の絵をしっかり見てもらうには、あまり人数が多いと無理があります。どうしても多くなってしまった時は大型絵本を使ったりもするのですが、絵本に無理をさせてしまっているなあと感じます。やはり1クラスぐらい、20~30人が理想ですね。今のまま、普通サイズの絵本で、絵が楽しめるような距離での読み聞かせを続けたいと思っています。
編集長:絵本も書いてらっしゃいますが、こちらはどうですか?
けいたろう:ご縁があって書かせていただきました。でも、もう既にたくさんの良い絵本があるので、「聞かせ屋。」としては、そういう良い本を伝えるということを大事にしていきたいなと。みなさん求めてくださいますし、自分の絵本も読まない訳にはいかないんですけれども、色いろな絵本がある中に自分の絵本もあるという立ち位置で行きたいと思っています。
編集長:読者の方へのメッセージをお願いします。
けいたろう:皆さんには、自分らしい絵本選びをしてもらえればと思います。
本棚からとっさに選んだ本を読むこともあると思いますが、お金や労力をかけて買ったり借りたりした本は、自分も読むのが楽しみですよね。子どもに「この絵本、何だか良いよね」と、提案や紹介をするように読む。そんな感じでいいのかなと思います。自分がその絵本を楽しんでいるかどうかって、伝わるのですよ。絵本はきっと、皆さんと子ども達をつなげてくれます。
-

-
読み聞かせ師・作家
夜の路上で、大人に絵本を読み始めた、聞かせ屋。
親子読み聞かせ、絵本講座、保育者研修会で全国を駆け巡る。絵本の文章、翻訳も手がける。保育士。一児の父。
作品に『どうぶつしんちょうそくてい』『おっぱいごりら』(アリス館)『まいごのたまご』(角川書店)『絵本カルボナーラ』(フレーベル館)など。