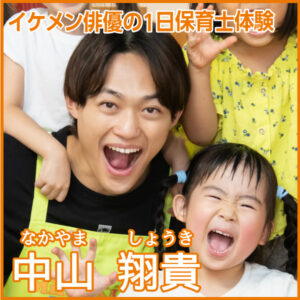人間への深い関心から心理学・保育・社会への思索に繋ぐ──大日向 雅美さん
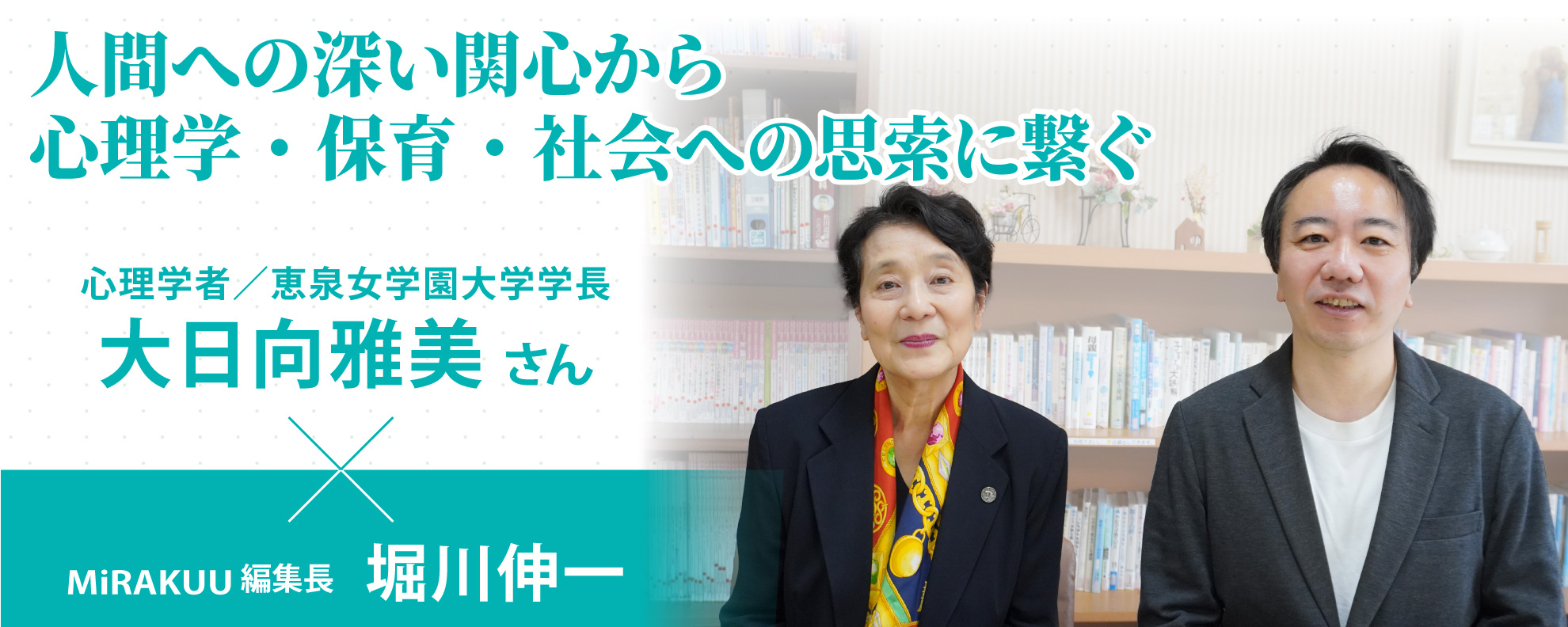
人の姿を浮かび上がらせる心理学
堀川:先生が保育や子育ての研究に進むきっかけは何だったのですか?
大日向:高校の時の現代国語の先生が、文学を通して、生きる人達の姿を教えてくださり、それがとても面白かったんです。その先生の勧めで入った大学が心理学専攻でした。
ところが当時の心理学は自然科学的な学問に近く、人の表情や声、感情が私にはほとんど見えてこず、興味が持てませんでした。そんな時、学科主任の藤永保先生が、若い頃にお書きになった論文を読みなさいと渡してくださったんです。
これがまた難解でつまらなかったんですが(笑)、なんとか最後までたどり着いたところで「心理学は特定の社会文化に生きる人間を対象とする。したがってその文化社会の特性なり欠陥をえぐるような視点を持って研究することが必要だ」という数行が記されていて、ハッとしました。
私が心惹かれていた近現代文学は女性の生き方や母子ものが多かったので、日本文化における母性へのこだわりを心理学的に捉えることができるのではないかと思ったんです。
すぐに先生に指導をお願いし、院に進んで。70年代初めに起きたコインロッカーベイビー事件(※)をきっかけに、母性偏重の日本文化の問題点を心理学的に解明しようと、10年かけて博士論文に繋がりました。
コインロッカーベイビー事件:生後間もない嬰児の遺体がコインロッカーで発見された事件。1970年代初期に頻発し、社会問題となった。
堀川:初めから心理学を志していたわけではないのですね。
大日向:そうなんです。ただその時々に「おかしい」と思ったことに取り組んできたことが今の道に繋がったと思います。
コインロッカーベイビー事件の時もそうです。「鬼のような母」「母性喪失の女」といった言葉がメディアを賑わせましたが、本当にその女性達はみんな、鬼のような母なのか、失格者なのかと疑問に思いました。もちろん母親が子どもを殺すなんてことは絶対あってはならないけれど、女性にはいつ何があっても完璧な育児ができる母性本能があると断じられることはとても怖かった。
「普通って何?」というのが私の口癖らしいんです。
私は子どもの頃みんなと同じことができなくて、幼稚園も小学校も嫌いで休みがちでした。でも家族は私の気持ちを尊重してくれて、そのおかげで私は人と違う自分を受け入れることができました。
幼い頃から普通と言われることや身の回りの色いろなことに疑問を持つ子で、それが心理学をやる上では役に立っているかもしれませんね。
変わりゆく保育の中で心に留めること

堀川:先生は保育・子育ての本質についてどのように考えていらっしゃいますか?
大日向:乳幼児期の保育に関わる仕事は、本当に崇高だと思います。保育園は今や社会を支えるインフラです。まずはご自分達の仕事の素晴らしさに自信を持っていただきたい。
不適切な保育のニュースが報じられて心が痛むこともありますが、ほとんどの保育士は子どもの成長を支える仕事に懸命に関わっているはずです。それだけに問題が起きたときには、萎縮せず、「自分達の何に問題があったのか」と見直して、プラスに転じてほしいと思います。
あえて言えば、人間に対する関心をさらに深めていただけたらとも思います。親御さん達から「保育士さんになかなか親の気持ちや日々の生活の状況を分かってもらえない」「忙しそうで相談しにくい」という声を聞くことがあります。保育の出発点は人への関心。子どもだけでなくその家族にも関心を向けることで、背景にある社会も見えてきます。
映画を観たり、文学、小説、ドキュメンタリーもたくさんお読みになって、人間の複雑で豊かな心模様や暮らしの営みを知ることは、保育へ関わる姿勢にさらに深みを持たせると思います。
堀川:保育が昔と変わってきていますが、その変化についてどう思われますか?
大日向:子育てや保育は不易流行だと思っています。時代の変化と共に変わる部分と、絶対に変わってはいけない部分とがある。子どもの懸命に育とうとする力を守り抜くことは変わってはいけない部分だと思います。
今そのことに多くの人が気づき、子どもをリスペクトする大切さに着眼する時代になったのは良かったと感じています。
一方で現代は情報が氾濫していて、子育てがとても難しくなっています。
少子時代ですが、かえって子育てに悩む親が増えています。子育てに悩むことはけっして悪いことではありません。一所懸命ゆえに悩み迷う面も強くなっていますので、そうした親の揺れに寄り添っていただけたらと思います。
もっとも、保育士さんも揺れていいと思います。常に正しくいるというのは無理ですし、不自然なことも出てくると思います。子どもの育ちをどう守るかという原点に立って、親と協働で日々を乗り切っていただけたらと思います。
一方、そもそも家庭や保育園だけの保育は無理です。子どもの育ちは地域の皆で見守ることが大切ですね。そのためには保育を“地域に開く”という視点をさらに取り入れていく。
たとえば地域の方々が学んで「子育て家族支援者」資格(厚生労働省認定資格)をとる動きも出ています。そうした地域の支援者の方々と一緒に子どもの成長を支えることは、これからの保育に一層、必要になってくると考えています。
現場の声は社会を変える原点
堀川:保育士さんの地位向上のために何が必要だとお考えですか?
大日向:保育・子育ての歴史を振り返ると、常にそのときどきの国の政治経済の影響を受けてきました。そうした歴史を精査することは、今、そして、これからを考える上でとても大切だと思います。その上で「こういう保育をしたい」「そのためにこういう環境が必要だ」と、現場の声をもっと上げていくことだと思います。
コロナ禍では保育園がライフラインだと実感した多くの親が、保育士の処遇改善を求める声を上げました。その後、待機児童が減りましたが、保育予算は下げずに質を上げるべきという動きへ繋がっています。だからこそ、今がチャンスなんです。
それにはエビデンスに基づいた発信が必要です、財務諸表や点検評価を読み込む力もつけたいですね。そこから現状を知り、改善点を語り合うことに繋がります。予算や制度の話になると難しく感じるかもしれませんが、自分達の働き方を変え環境を良くするための基本でもあると思います。
また保育園は今の社会の問題をとらえる最前線にあると言えます。保護者からのクレームは社会の歪みの発露とも言えますし、虐待にしても最初に発見できるのは保育園で、家族関係の課題や実態を見ることができることでしょう。
そういう意味では、人文社会科学的視点で子どもの育ちとそれにかかわる諸要因のデータを現場で積み重ねていくことのできる仕事であり、社会を変えていく原点となる仕事だと思います。
堀川:最後に、読者へのメッセージをお願いします。
大日向:AIの台頭で今ある仕事の何割かがなくなると言われていますが、保育は最後まで残る仕事だと思います。子どもが育つ姿、命が育つ姿を楽しめるという意味で、幸せな環境にいると思って、保育を精一杯楽しんでください。困難も少なくないと思いますが、それを乗り越える力も、保育の意義を確認し、楽しむ心が原点となるのではないかと思います。
(MiRAKUU vol.51掲載)
-

- 心理学者/恵泉女学園大学学長
恵泉女学園大学学長。専門は発達心理学。学術博士(お茶の水女子大学)。
半世紀余り母親の育児不安を研究し、NPO法人あい・ぽーとステーション代表理事として地域の子育て支援活動も実践。
『母性愛神話の罠』『母性の研究』(日本評論社)他多数。