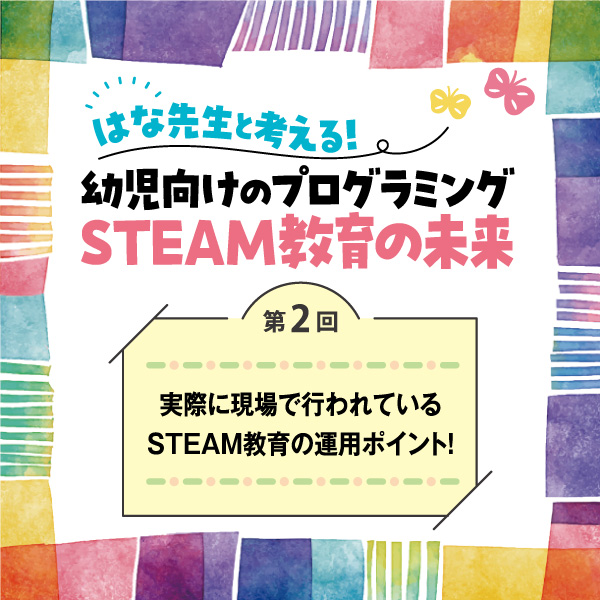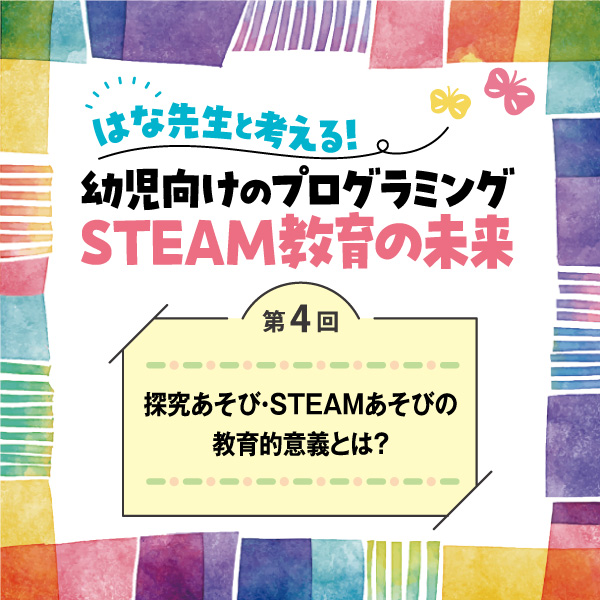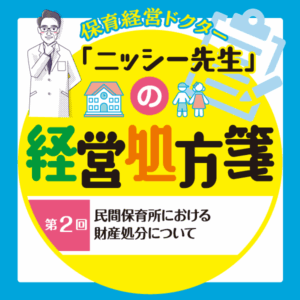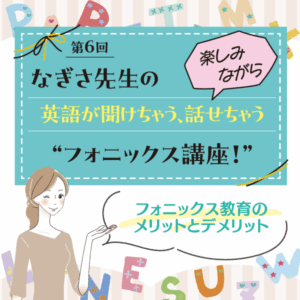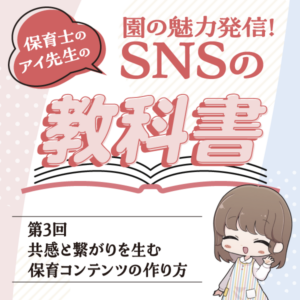第3回 STEAM教育、最初の一歩は「落ち葉」から──はな先生と考える! 幼児向けのプログラミングSTEAM教育の未来
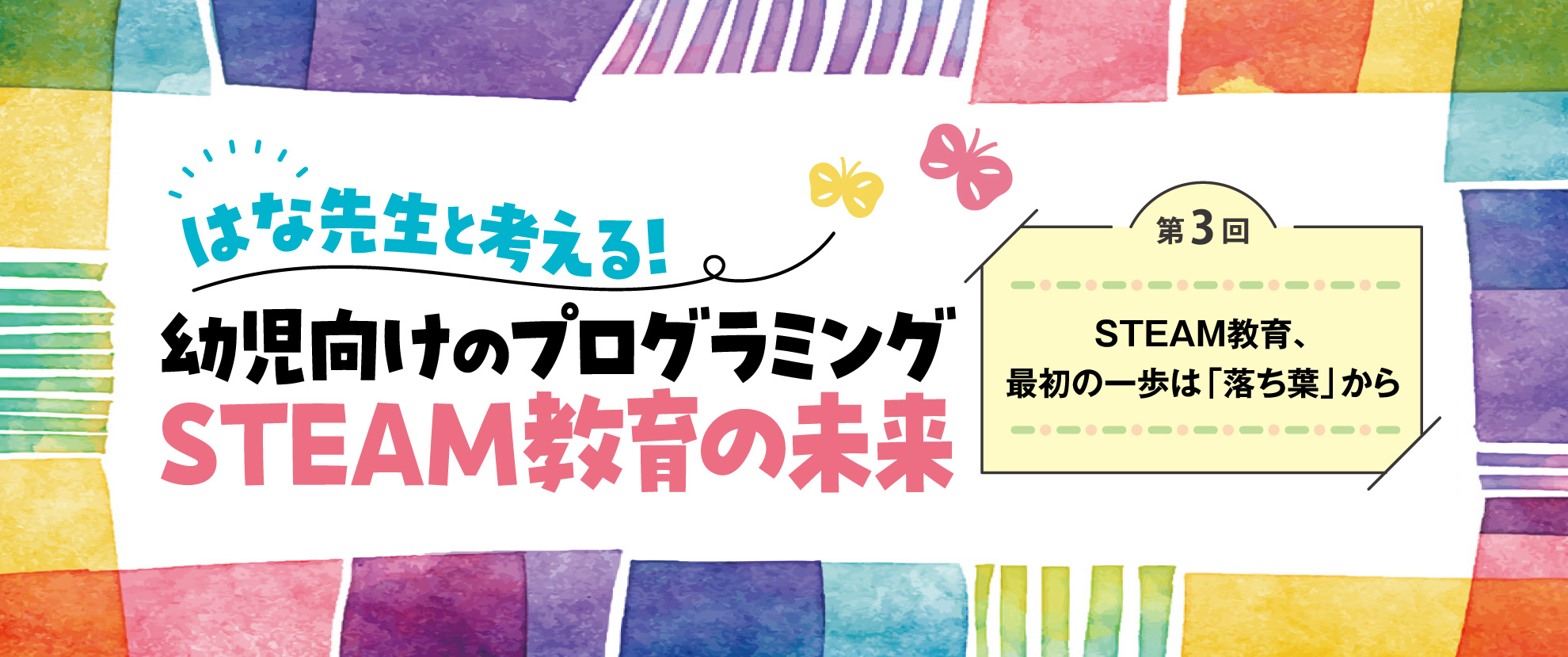
こんにちは! はな先生です。
第3回は「STEAM教育に興味はあるけれど、何から始めればよいか分からない」そんな先生方に向けて、今回は自然あそびとつながるSTEAMの入り口として簡易なカリキュラムをご紹介します。
実践のコツは3つ
まず、実践のコツは3つだけ!
- STEAMの5要素を意識して複数取り入れること。
- いつもの保育の延長として捉えること。
- 子どもへの「問いかけ」を大切にすることです。
テーマは「落ち葉をつかって空気の力を体験しよう!」
今回のテーマは「落ち葉と空気」。お散歩や園庭での外遊びで子ども達が拾ったお気に入りの落ち葉を使い、ふしぎな“落ち方”の違いに注目します。
- ティッシュでクイズからスタート
まずはティッシュを使ってクイズ。「丸めたティッシュとふわふわのティッシュ、どっちが早く落ちる?」と問いかけ、実際に落としてみます。「丸めた方が早い!」という発見から、子ども達の探究が始まります。
- 落ち葉で再チャレンジ
次に「じゃあ、拾った落ち葉だとどうかな?」と展開し、ティッシュとの違いを実際に比較・観察します。「広げたまま」「折りたたんで」など、子ども自身が試しながら発見していきます。
- 空気抵抗の仕組みを伝える
観察のあとは、空気抵抗について簡単に伝えます。風船や紙飛行機の例を出し、「広がったものは空気をたくさん受けるから、ゆっくり落ちる」といったイメージを図やジェスチャーで見せると、理解が深まります。「空気抵抗」という言葉を肌で感じてもらいましょう。
- 改造して“色いろな落ち方”に挑戦!
続いて、落ち葉の改造実験へ。真ん中をくり抜く、ギザギザに切る、羽をつける、重りを貼る、折り曲げる、のりをつける……など、子ども達は自由な発想で試しながら工夫を重ねます。


保育の延長でSTEAMが始まる
この活動には、科学的観察、技術的工夫、構造設計、芸術的表現、落下時間の比較など、STEAMの要素が自然に詰まっています。
造形や散歩、対話の延長線でできるため、無理なく保育に取り入れられます。
おわりに
はじめの一歩に、特別な教材や時間は必要ありません。落ち葉1枚が、子ども達の「なんでだろう?」を育てるSTEAMの入口になります。ぜひ、秋の園庭で問いの種をまいてみてください。
【次回予告】探究あそび・STEAMあそびが持つ“教育的意義”
次回は、探究あそび・STEAMあそびが持つ“教育的意義”にフォーカスします。
子ども達の「考える」「試す」「工夫する」力が、どのように育ちに繋がっていくのか? 現場での実践ポイントをお届けします。
(MiRAKUU vol.52掲載)
-

- 株式会社MIRIDE代表取締役
新卒入社したITベンチャー企業でいくつもの新規事業を成功に導き、取締役を歴任。
この経験より幼少期の非認知能力の重要性を実感し、未来の子ども達のために起業、当社設立。