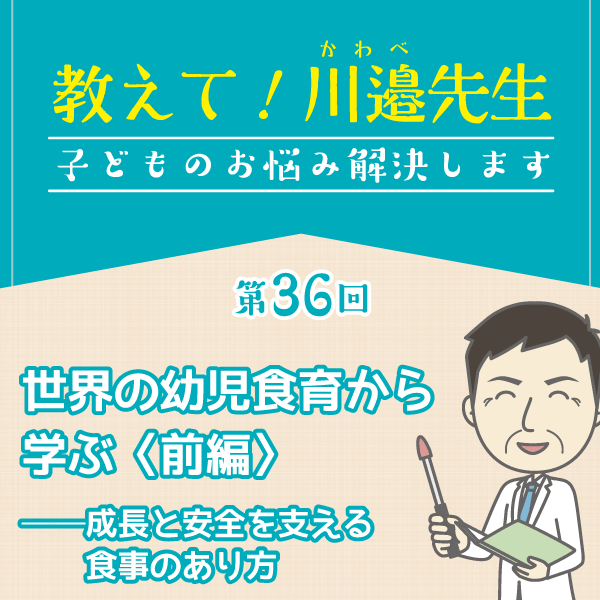第35回 現代の子ども達が直面している問題とは?
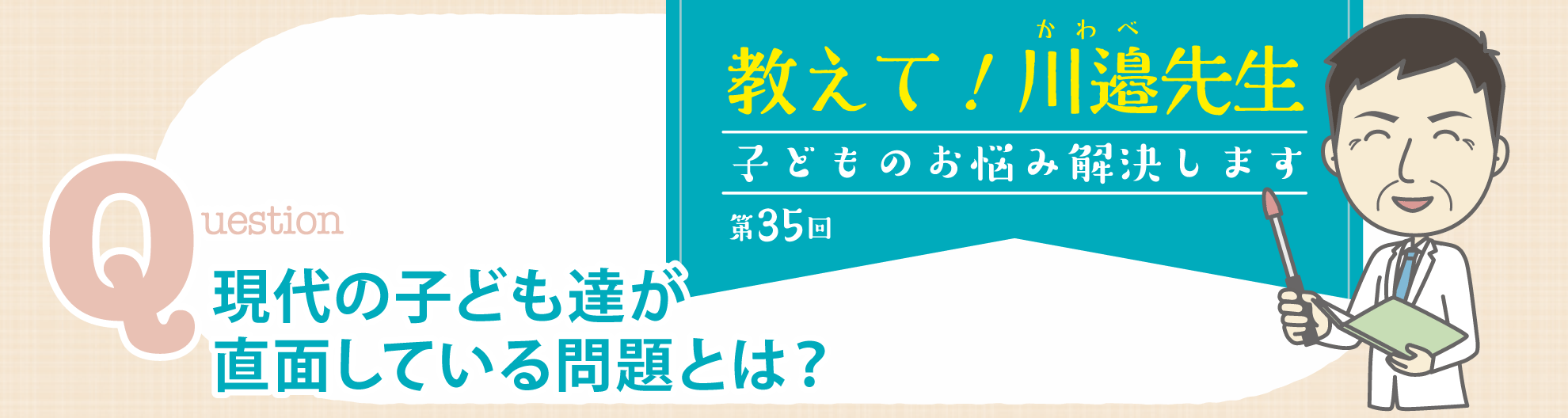
現代社会が抱える子どもの成長への様々な影響と、私達大人がどのように子どもの未来をサポートできるかについてお話ししたいと思います。
現代と過去──何が変わったのでしょうか?
60年前には、子どもの歯並びの問題や発達に関する悩みはほとんど見られませんでした。今の時代は、生まれたらすぐに歯並び矯正の費用を積立しましょうという時代。おかしいと思いませんか?
現代は生活環境、教育、医療のあり方が大きく変わり、スマホやゲーム、塾・習い事といった外部からの刺激や、親からの期待・プレッシャーが子ども達の心身に影響を及ぼすようになりました。
この変化は、子ども達が本来持つ「生きる力」にも影響を与えていると感じる方が多いのではないでしょうか。
脳幹──子どもの健康の土台
まず注目したいのが「脳幹」です。脳幹は、呼吸、睡眠、食欲など、私達が生きるために欠かせない機能を司る本能的な部分です。また、危険を察知する力や体のバランスを保つための自己防衛本能も、この脳幹がしっかりしていることで発揮されます。
しかし現代の環境では、長時間のスマホ使用やゲーム、過剰な習い事、そして大人からの過度な期待が、子ども達の脳幹の発達に悪影響を与える可能性があります。結果として、五感の働きが低下し、危険に対する察知能力やバランス感覚が十分に育たない恐れがあるのです。
紙おむつのために五感がなくなり、今の時代6歳を過ぎてもおむつが外せない子ども達が多いということも知ってほしいですね。そして脱肛。痔の薬の宣伝は今や高校生、中学生をもターゲットにしています。
「五感」とは、私達が周囲の世界から情報を得るために使う5つの感覚のことを指します。具体的には以下の通りです。
-
視覚
目を通じて光や色、形などの情報を捉える感覚。
-
聴覚
耳を通じて音を感じ取り、音の高さや大きさ、リズムなどを認識する感覚。
-
嗅覚
鼻を使って香りや臭いを感じる感覚。
-
味覚
舌を通じて、甘味、塩味、酸味、苦味、旨味などを感じる感覚。
-
嗅覚
皮膚やその他の感覚器官を通じて、温度や硬さ、質感、圧力などを感じる感覚。
これらの五感が協力して働くことで、私達は環境を総合的に認識し、適切な行動を取ることができます。姿勢が悪いとか行動がおかしい場合には、この医療では治せない五感に問題があるのです。
教育のあり方を再考する──五感と自己肯定感の育成
現代の教育は、単に知識を詰め込むだけではなく、子ども達が自ら考え、感じ、表現する力を育むことが大切です。そこで、以下のポイントを改めて考えてみてください。
-
五感を刺激する体験型学習
自然や地域社会との触れ合い、実際の体験を通して、視覚・聴覚・触覚などを豊かに育てることが重要です。
-
自己肯定感の育成
画一的な評価に頼るのではなく、子ども達が自分の意見を持ち、自分を大切にする心を育む教育が求められます。1日に3万回は行われているという「判断」ができなくなっているのは、過保護、過干渉、矛盾の与えられた人生だからです。
-
自ら考え行動する力
大人の言うことをただ受け入れるのではなく、疑問を持ち、考え、判断する力こそが将来の自立へと繋がります。成長・発達とは、様々な時期にその都度親からの自立ができ、社会に対しての自律ができることです。
医療の未来──予防と個々に寄り添うケア
現代の医療は、病気になってから治療するだけではなく、日々の生活習慣の見直しや、予防医療へのシフトが必要です。(保健医療は疾病後追い型保険ですので、健康を向上させるためには使えません。病気が増えると医療機関の収益が上がるシステムです。予防は行政が行う、自由診療で行うことですが、100年以上前には予防が主体でした。)
また北欧のように、一人ひとりの状態や気持ちに寄り添い、保険制度のように商業化や画一的な対応ではなく、個別のニーズに合わせた予防医療教育が求められています。
こうしたアプローチは、伝統的な日本の健康習慣にも学ぶところが多く、生活全体を見直す良い機会となるでしょう。
親としてできること──日常の中でのケア
親として、子ども達が健やかに育つ環境を整えるために、以下の点を日常生活に取り入れてみましょう。
-
自然と触れ合う時間の確保
できるだけ外で遊び、四季折々の自然を感じることで五感を刺激し、ワクワク・ドキドキで日常を過ごし、家に帰ったらリラックスする時間を持つことが大切です。
-
適度な運動と十分な睡眠
規則正しい生活リズムは、脳幹の発達を促進し、心身のバランスを保ちます。
-
ストレスフリーな環境作り
ストレスは必要ですが、過剰なストレスを発散するには遊びとしての運動以外にはありません。習い事や塾などの過度なスケジュールを見直し、子どもが自由に遊び、自己表現できる時間を尊重しましょう。
-
社会全体で支える意識
家庭だけではなく、保育園や地域社会と連携し、子ども達が安心して成長できる環境づくりに協力していきましょう。
まとめ
本来子ども達は冒険王。交感神経優位でワクワク・ドキドキで動き周り、些細なことで泣いたり笑ったりします。しかし現代社会では、遊ぶ場所も裸足で走る運動場も、飲める川の水すらなくなりました。
泣いたらしなくてもいいという教育で、自分の生きる力さえ信じられず、子ども達は海図という目標もコンパスという指標もないまま育っていきます。そして大人になっていきなり社会人だと言われたり、子どもができたらいきなりお母さんだと言われて戸惑ったり、全く経験が受け継がれていない世界で生きて、突然現実を投げつけられるのです。
引きこもりという日本特有の病気は、今や数百万人かもしれないという時代です。たくさんの失敗を重ねて成功体験は育つのですから、何も失敗もしたことがないということは何も社会に対応することはできていないということです。過保護、過干渉そしてその反対の矛盾の世界に、時間が過ぎて初めて気付くのです。
しかしながら、現代社会は過去の成功体験だけでは対応できない複雑な課題を抱えています。脳幹の発達という新たな視点から、教育と医療のあり方を見直し、子ども達が本来持っている生きる力を最大限に引き出すことが、これからの社会にとって不可欠です。
私達大人一人ひとりが、子ども達の健やかな成長を願い、日々の生活の中でできる小さな工夫を積み重ねることで、安心して未来へ羽ばたける社会を築いていきましょう。
皆さまのご家庭で、子ども達と共に笑顔あふれる毎日を送れるよう、心から願っております。
(MiRAKUU vol.50掲載)
お問い合わせボタンからお気軽にご質問ください。
ご質問は、誌上・web上で公開されることがあります。また、必ずしも質問が取り上げられるとは限りません。ご了承ください。
-

- 新橋 未来歯科 院長
姿勢咬合セミナー主幹(27年以上続く姿勢と噛み合わせの歯科医師向けのセミナー)
Ken'sホワイトニングセミナー主幹1984年静岡県菊川市にかわべ歯科を開業。2011年新橋に未来歯科開業。
従来の疾患中心型治療ではなく、「細菌単位でのお口の中のリスクを知り、その結果に基づき改善していく」「食事内容の分析・アドバイス」「姿勢指導や、呼吸などのアドバイスによる体質改善」「患者様の未来の目標設定」をコンセプトにした「予防」診療を行う。
歯科医・歯科衛生士向けの各種セミナー、DMMでのオンラインサロン等も精力的に行なっている。
『かわべ式 子育てスイッチ ~生まれた瞬間からグングン発達する88の秘訣』(エッセンシャル出版社)好評発売中。
ホームページ:https://miraishika.com/
未来歯科アカデミー:https://miraishika.com/academy/
未来歯科アカデミーでは実際に未来歯科に来ていただくほか、リアルタイムでの質問も受けています。